ここではジョン・トンプソン編の「トンプソンのハノン」を紐解いて行きます。
おすすめポイントと詳しい内容をおすすめします。
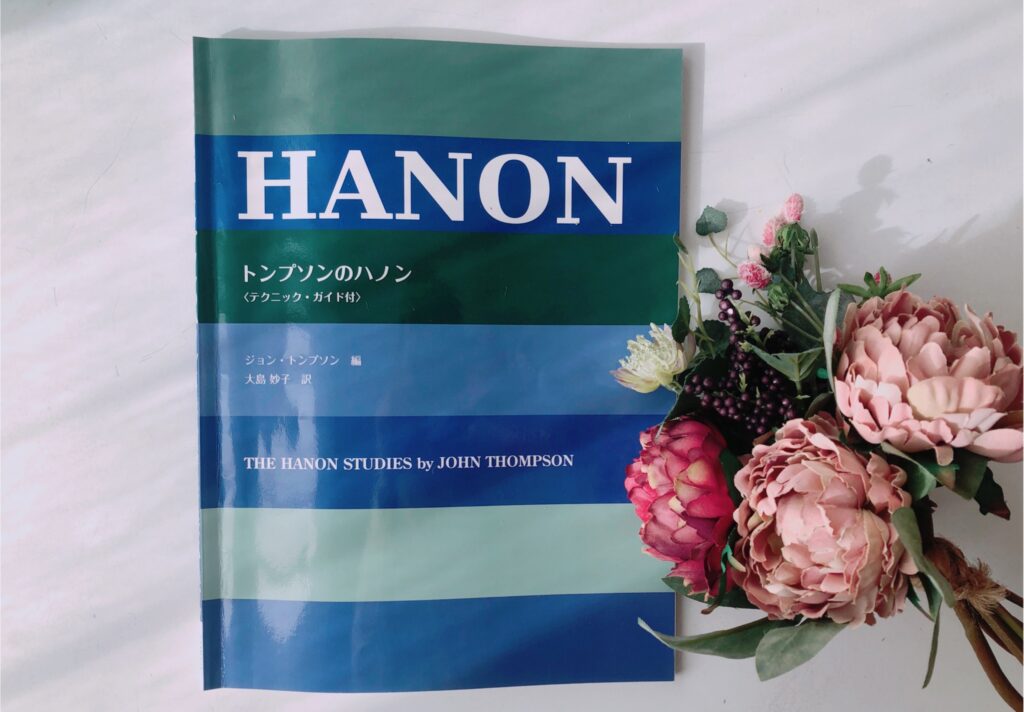
- 1. ポイント1:基本的な打鍵法を詳細に
- 2. ポイント2:初級者でも使いやすい
- 3. ポイント3:単調になりがちなハノンを豊かに
- 4. こんな人におすすめ
- 5. このテキストに足りないところ
- 6. 内容は?
- 6.1. 目的は?
- 6.2. 対象は?
- 6.2.1. 打鍵法とは?微細な変化に富んだ打鍵ほうのためにまずは基礎をしっかり
- 6.2.2. 打鍵法の発展は?生徒から自然と生まれる
- 6.2.3. 本書の方法は?単純明快に
- 6.2.4. 習得方法は?腕と手首を自由に
- 6.2.5. お手本は完璧に
- 6.3. 第1部(1〜20):ピアノ奏法の基となるタッチ
- 6.3.1. 1〜10番:基本の奏法
- 6.3.2. 復習:速いスピードで弾けるようにするためのリズム・ドリル(練習表)
- 6.3.3. 11〜20番:復習
- 6.4. 第2部(21〜38):独立した指の発達、ヴィルトゥオーゾへ
- 6.5. テキスト概要
ポイント1:基本的な打鍵法を詳細に
基本的なピアノの打鍵方法を細かく明確に、図と言葉で説明しています。場合によって写真やイラストがあり、イメージがしやすくなっています。
「スタッカート」を例にあげてみると、教本などによっては「短く切って弾く」とだけ書かれていますが、実際には様々な弾き方があります。
このテキストでは、「手首のスタッカート」「指のスタッカート」「前腕のスタッカート」と三種類のスタッカートを学びます。
実際に曲を演奏するときに使う表現を、「ハノン」という各指の俊敏さ、独立性、均等性を目標とした練習曲を使って効率的に習得することができます。
ポイント2:初級者でも使いやすい
「ハノンピアノ教本」は音符が細かく音が多いので、初級者の方の場合は楽譜を読むことだけでも負担になってしまいがちですが、
「トンプソンのハノン」は四分音符からはじめるので、ある程度楽譜の規則がわかるようになった初級者の方でも使いやすくなっています。
曲を数曲演奏できるようになった段階で使用し始めると、演奏がより豊かになり、曲の魅力をさらに感じられるようになると思います。
ポイント3:単調になりがちなハノンを豊かに
機械的な練習に陥りがちな「ハノン」ですが、打鍵法を習得するという目的を持って集中して練習することで、単調な繰り返しを避けることができます。
指や手首、腕だけでなく、その音色の変化に関心を向けて集中して練習することで、効果的なテクニック練習ができます。
こんな人におすすめ
- ピアノの基本的な打鍵法を知りたい方
- 豊かな音色で演奏したい方
- 自分の演奏が単調たと感じている方
- テクニックを身に付けたい方
このテキストに足りないところ
- レッスンでの使用ではなく、独学の場合イラストや解説だけでは限界があるかもしれません。
動画サイトなどを参考に利用することをおすすめします。 - 電子ピアノやキーボードの場合、物によっては音色の変化を感じづらいことがある。
次に詳しい内容をお伝えします!
内容は?
指の練習として定番の「ハノン教則本」の38番までの曲を、トンプソンが1曲毎にテクニックの解説をつけ、編纂しています。
編者のトンプソンは、「トンプソン 現代ピアノ教本」の著者です。
「トンプソン 現代ピアノ教本」についてはこちら↓をご覧ください。
「ハノン教則本」は3部に分かれていて、38番までというのは第2部の途中までです。
39番以降はスケールとアルペジオの練習、「高度なテクニックを身につけるための練習」と題された第三部が続きます。
その前の段階までを、トンプソンが解説をつけて編纂しています。
訳者の大島妙子さん曰く、トンプソンは子どもたちがあるレベルに達したらハノンの勉強は欠かせないとしつこく勧めていたと言います。
目的は?
巻頭の「はじめに」に本書の目的や使用方法など著者の思いが書いてあるのでまとめます。
- 動きの速い独立した強いバランスの取れた指を追求することと
- 表現豊かなピアノ演奏に欠かせない様々な基本的な打鍵法を身につけること
- 若いピアニストが本書で基礎となる打鍵法を理解し、それを難易度が高くなっていく曲の中で応用できるようになること
- 初歩の段階の生徒が、音を出すことのみに集中せず、これらの打鍵法を理解した上で演奏し、音質が変わり、曲に対する正しい解釈の第一歩を踏み出すこと
対象は?
対象は、ピアノを弾き始めたばかりの人です。
著者であるトンプソンは、以下のように考えていと言います。
コンサート・ピアニストのごく基本的な打鍵法は、ピアノを弾き始めたばかりの人たちにも教えなくてはならない。
「トンプソンのハノン」はじめに
音符を読むことができるようになった初級の方から使うことができます。
打鍵法とは?微細な変化に富んだ打鍵ほうのためにまずは基礎をしっかり
打鍵とは鍵盤を打つこと、沈めることです。
ピアノ演奏は鍵盤をどのように打ち、どのように沈めるのかで音色を変化させます。
その打鍵法について、著者は以下のように書いています。
各々の打鍵法は、数限りない微細な変化があります。
少しずつ微妙に違う打鍵法を、基礎の打鍵法を身につける前に教えようとするのは、(中略)かえって混乱を呼び起こします。
無理な力を入れたり、筋肉を固くしたり、テクニックを重視しすぎた姿勢を生み出すことになるでしょう。
「トンプソンのハノン」はじめに
まずは基礎の打鍵法を身につけることが大切です。
打鍵法の発展は?生徒から自然と生まれる
基礎の打鍵法を身に付けるとどうなるのでしょうか。その発展について著者は次のように書いています。
ピアノを弾くことは、歩くこと、走ることなどと同じように自然なプロセスをたどっていくものです。
根本となる基礎を身につけ、リラックスして弾くことができれば、そこから数え切れないほどの様々な変化に富んだ打鍵法が自ずから生まれます。
「トンプソンのハノン」はじめに
また、教師の独りよがりの教え込みによって、生徒自身から自然に生まれてくるべき打鍵法のプロセスを妨げてしまうことないように注意を促しています。
本書の方法は?単純明快に
以上のような理由で本書は、単純明快に説明することがスローガンだと言います。
打鍵法は根本に沿ってのみ述べ、細かい説明をこの本では避けているとのことです。
習得方法は?腕と手首を自由に
最初の3曲(2つの音、3つの音、4つの音のフレーズ)の課題で、「ドロップ(落とす) ロール(回す)」の動きを身につけます。
この動きは、腕と手首が自由に使えるように導き、レガートも手を固くせずに弾けるようになります。
お手本は完璧に
様々な打鍵法を教えたい場合、先生が実際に生徒の前で弾いて見せることが最も早く、確かな方法だと言います。
その弾き方が正しくなければ、生徒も間違ったことを身につけてしまう。
先生が実際に弾いて見せる時はできる限り完璧であるように注意が促されています。
それでは実際に内容を見て行きます。
第1部(1〜20):ピアノ奏法の基となるタッチ
第1部は二つの部分からできてきます。
- 1〜10番:基本の奏法を学びます
- 復習:速いスピードで弾けるようにするためのリズム・ドリル(練習表)
- 11〜20番:これまで学んだことを合わせて演奏します
1〜10番:基本の奏法
元々の「ハノン教則本」は16部音符で書かれた音型を2オクターブに渡って繰り返し弾きますが、
こちらの「トンプソンのハノン」1〜10番は、四分音符で、1オクターブに編曲されています。
そして、学ぶテーマのスラーやスタッカートがはじめから書かれています。
1曲ごとに文章による解説書かれています。場合によっては写真や楽譜でわかりやすく解説されます。
1~10番で学ぶことは以下のようになっています。
- 2つの音のフレーズ
- 3つの音のフレーズ
- 4つの音のフレーズ
- 手は動かさないで、指を上げてのレガート
- 手首のスタッカート
- 指のスタッカート
- 前腕のスタッカート
- ポルタメント
- 鍵盤に指を近づけたレガート
- 回すような動きの打鍵(回転奏法)
各テーマにはイメージしやすいようなタイトルがついています。
例えば「2つの音のフレーズ」は「足の不自由なアヒル」、「回すような動きの打鍵(回転奏法)」には「噴水」などです。
復習:速いスピードで弾けるようにするためのリズム・ドリル(練習表)
1〜10番の復習をします。
11通りのそれぞれ違ったリズムで練習をします。付点のリズムや3拍子、3連符、16分音符などです。
様々なレガートで弾くことや、強弱をつけて練習することを勧めています。
これらの10曲を16分音符の速さで弾けるようになったら、次の11番に入ります。
11〜20番:復習
10番までに学んだことを1曲の中に2つ以上合わせた曲で練習していきます。
例えば、
11番は、「2つの音のフレーズ」と「4つの音のフレーズ」の組み合わせ、
15番は、2小節ごとに、10個の打鍵法をかわるがわる使って弾きます。
第2部(21〜38):独立した指の発達、ヴィルトゥオーゾへ
21〜38番は「復習」で実践したようなリズムの練習を行います。
付点のリズム、3連符、6/8拍子、スラー、スタッカート、16分音符、など、それぞれの曲で違ったリズムや奏法で練習します。
21番から解説はありません。
以上、内容を詳しく見てきました。
テキスト概要
- 「トンプソンのハノン」(The HANON STUDIES by John Thompson)
- 著者:ジョン・トンプソン
- 訳者:大島妙子
- 出版1937年(日本ライセンス版は2009年)
- ヤマハミュージックメディア
- レベル:初級〜中級
執筆者

ピアノ講師、ピアノ弾き、ピアノ教本の専門家。
自宅教室で指導の傍ら演奏活動を行う。
「自分で奏る喜びをたくさんの人に」をテーマにwebサイト「ピアノ・レッスンズ」を運営。
チャイルドカウンセラー取得。
中高教員免許(音楽)取得。
2児の母。


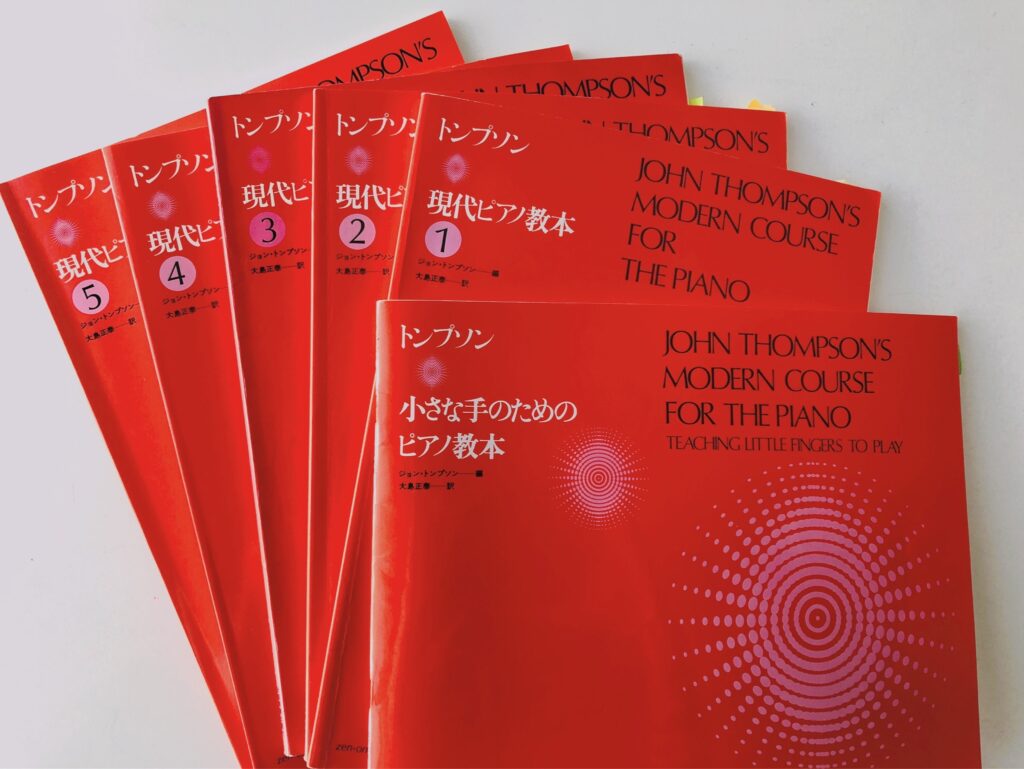

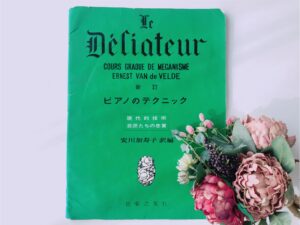
“「トンプソンのハノン<テクニック・ガイド付>」ポイントと内容をご紹介!” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。