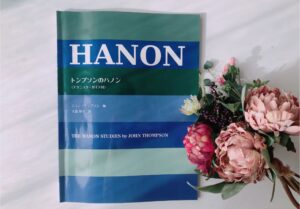ここでは「ピアノ・アドヴェンチャー テクニック&パフォーマンス」を紐解いていきます。
おすすめのポイントと詳しい内容を解説します!

ポイント1:指、手首、腕、重さがテーマ
「テクニック」というと、「ハノン・ピアノ教本」のような指を様々な方法でたくさん動かし、指を鍛えるということがイメージされがちですが、こちらのテキストは身体の各部分を意識した演奏方法を身につけるテクニックです。
ごく少ない音を鳴らす時から、指や手首を意識します。
イメージしやすい例を使った説明や、図や写真で身体の使い方を学びます。
レベルが上がるにつれて、腕や、腕の重さへ注意を向けていきます。
それらを総合して、スタッカートやスラー、メロディを歌わせる方法、黒鍵の弾き方、ポジションを移動する方法、フレーズの歌わせ方などの演奏につなげていきます。
ポイント2:著者の作品からクラシックの有名な曲へ
レベル1では主に著者の作品を弾きますが、レベル3、レベル4&5では、有名なクラシック曲を演奏します。
積み上げてきたテクニックをもとに、作品を演奏するパフォーマンスにつながります。
ポイント3:単体でも使える
メインテキストである「レッスン&セオリー」の併用テキストではありますが、テクニックの習得と曲集として単体でも使用することが可能です。
身体の使い方を含んだテクニックに細かく触れている導入テキストはあまり多くないので、こちらのテキストで補うとより音を豊かに楽しむ演奏へとつながります。
このテキストに足りないところ
- 「ピアノ・アドヴェンチャー 」のアプリに対応していない。
- 説明は詳細で丁寧だが動画や音源はなく、レッスンでお手本を示すことが前提とされているので、独学の場合に壁を感じることもあるかもしれません。
こんな人におすすめ
- 「ピアノ・アドヴェンチャー レッスン&セオリー」を使用している方
- 手、手首、腕、重さの使い方を学びたい方
- 少し音に変化をつけたいと感じている方
- テクニックに行き詰まりを感じている方
詳しい内容は?
進み方は「ピアノ・アドヴェンチャー レッスン&セオリー」に沿っています。
「レッスン&セオリー」に対応した、レベル1、2A、2B、3、4&5の全5冊です。
各巻の内容も「レッスン&セオリー」のUNITに対応して構成されています。
巻頭にそのテキストで学ぶ4〜5つの「テクニックのひけつ」が紹介されます。
各UNITは、テクニックの秘訣を学ぶ短い曲と、「エチュード」「パフォーマンス」の3つの部分から構成されています。
「ピアノ・アドヴェンチャー」シリーズのメソッドや、「レッスン&セオリー」にいついては、こちら↓で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
目的:正しい身体の使い方によるテクニックと、豊かな音楽表現
各巻のはじめに、全巻に共通する目的をが書かれているので引用します。
ピアノ演奏に不可欠な、身体や腕、手首、指すべてを使って弾くテクニックを学びます。
「ピアノ・アドヴェンチャー テクニック&パフォーマンス レベル1」レベル1について
高度なピアノテクニックを、生徒が理解しやすいたとえを用いながら、初歩の段階から学習します。
一度、悪いクセがついてしまうと、後から修正することはとても困難です。
本書を使って、早い段階から正しいテクニックを身につけることが重要です。
つまりここでは、悪い癖がつかないように早い段階から正しい身体の使い方を身につけます。
さらに、
ピアノ演奏の目標は芸術性であり、テクニックはそれを実現させるための手段です。
「ピアノ・アドヴェンチャー テクニック&パフォーマンス レベル1」レベル1について
本書では、各ユニットに「エチュード」と「パフォーマンス」の曲があり、
テクニックと芸術性を同時に学び、豊かな音楽表現を引き出します。
「エチュード」でテクニックを習得し、「パフォーマンス」では、その身につけたテクニックで芸術性を磨きます。
主に学ぶ「テクニックの秘訣」
「テクニックの秘訣」はテキストが進むとレベルアップして行きますが、まとめると共通しているテーマがあります。
テーマごとにまとめてみました。
手の形
- 丸い手の形(レベル1)・・・手のコップ
- しっかりとした指先(レベル2A)・・・丸い鳥かご
- スケールを弾く丸い手(レベル3)・・・指の花火(手を縮める)
親指の使い方
- 軽い親指(レベル2A)・・・おどる親指
- 軽い親指(レベル2B)・・・親指移動
手首の動き
- 手首のリラックス(レベル1)・・・浮き上がる手首
- 浮き上がる手首(レベル2A)・・・虹を描く
- スラーの手の動き(レベル2B)・・・筆の動き
- 優しく離す(スラーの終わり)(レベル3)・・・ため息
- 手首で円を描く(レベル4&5)
指の動き
- 指の独立(レベル1)・・・ピアノの蓋を閉じて音なし練習
- 両手を一緒に動かす(レベル2A)・・・チームワーク
腕の重さ
- 重たい腕(レベル2B)
- メロディを歌わせる(レベル3)・・・腕の重みを使ってメロディを歌わせる
- まっすぐ揃える(レベル4&5)・・・前腕〜手〜指先をまっすぐ揃えて腕の重みを伝えて弾く
- 落として弾ききる(レベル4&5)・・落とした腕の重みのエネルギーを使ってフレーズを弾ききる
これらの「テクニックの秘訣」をもとに、後半に行くにつれてスケール・アルペジオや和音の展開形の練習を含むエチュードを弾きいていきます。
次に各巻の内容を見ていきます。
レベル1
全巻共通してまずはじめに「テクニックのひけつ」を図と言葉と短い曲で学びます。
ここでは4つの「テクニックのひけつ」を学びます。
- まるい手の形(手のコップ)
- 手くびのリラックス(浮き上がる手首)
- かるく手を弾ませる(きつつきトントン)
- 指の独立(音なし練習)
続いて「レッスン&セオリー レベル1」と同じタイトルのUNIT1〜10があります。
多くが著者の作品を弾きますが、それに加えて以下の作曲家の曲も弾きます。
- ツェルニー
- バイエル
- グルリット
- テュルク
- ケーラー
さらにトラディショナルな曲もあります。
ほとんどの曲に伴奏パートがついてます。
レベル2A
ここでは5つの「テクニックのひけつ」を学びます。
- しっかりとした指先(丸い鳥かご)
- 両手を一緒に動かす(チームワーク)
- 軽い親指(おどる親指)
- 素早い指の動き(指のスピード)
- 浮き上がる手首(虹を描く)
著者の作品に加えて、以下の作曲家の曲を弾きます。
- ウェーバー「狩人の合唱<魔弾の射手>より」
- モリッツ・ボーゲル
- ツェルニー
- ケーラー
- バイエル
そのほか、巻末には5本指のスケール練習があります。
長調は全ての調(13個)、短調は白鍵から始まる7つの調を弾きます。
レベル2B
ここでは4つのテクニックのひけつを学びます。
- 腕の重み(腕の重み)
- スラーの手の動き(筆の動き)
- 軽い親指(親指移動)
- ペダルをつなぐ(ペダル・リズム)
レベル3
ここでは4つのテクニックのひけつを身につけます。
- スケールを弾く丸い手(指の花火)
- 優しく離す(ため息)
- メロディを歌わせる(メロディ作り)
- 跳ねる(指のバネ)
著者の作品に加えて、以下の作曲家の曲を弾きます。
- ベイリー「ロング・ロング・アゴー」
- プレトリウス
- ベートーヴェン「アレキサンダー・マーチ」
- カルッリ
- グリーグ「山の魔王の宮殿にて<ペールギュント>より」
- リュリ
- タチアナ・セルゲエワ
- ツェルニー
- バッハ
レベル4&5
ここでは5つのテクニックのひけつを身につけます。
- まっすぐ揃える(平均台)
- 落として弾ききる(フレーズのきらめき)
- 手首で円をえがく(手首で導く)
- きっちりしたスタッカート(スタッカート・マシーン)
- ローテーション(ふりこの動き)
著者の作品に加えて、以下の作曲家の曲を弾きます。
- ツェルニー
- ビール
- バッハ
- ブルグミュラー「天使の声」
- クレメンティ
- グルリット
- エルメンライヒ「つむぎ歌」
- プッチーニ「私のお父さん<ジャンニ・スキッキ>」
- ゴセック
- コンコーネ
- モーツアルト「交響曲 第40番 第一楽章より」
- ベルティーニ
- シベリウス「フィンランディア」
- ラベル「ボレロ」
- ベートヴェン「エリーゼのために」
以上各巻の内容を見てきました。
教本概要
- 「ピアノ・アドヴェンチャー テクニック&パフォーマンス」導入書、1、2A、2B、3、4&5(全6巻)
- 著者:ナンシー・フェイバー、ランディー・フェイバー
- 訳者:近藤真子
- 2020年出版
- 全音楽譜出版社
- 併用テキスト:「ピアノ・アドヴェンチャー レッスン&セオリー」導入、1、2A、2B、3、4&5(全6巻)
- レベル:導入〜中級程度
楽しいピアノライフを!
執筆者

ピアノ講師・ピアノ演奏家のピアノレッスンズ。
自宅教室で指導の傍ら演奏活動を行う。
「自分で奏る喜びをたくさんの人に」をテーマにwebサイト「ピアノ・レッスンズ」を運営。
中高教員免許(音楽)取得。
チャイルドカウンセラー取得。