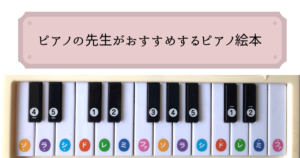この記事はアフィリエイト広告を利用しています。
今回は田丸信明編著「新訂ピアノの森」 を紐解いていきます。
後編では、実際に全て演奏して感じたポイントをご紹介します。
前編では内容を紹介していますので、合わせてご覧ください。

ポイント1:童謡など子どもが親しみやす曲が弾きやすい伴奏で
ピアノをはじめたばかりの方が対象の第1巻は特に、生活の中で親しむだろう曲が多く収録されています。
有名な童謡は次のようなものです。
- 「ちょうちょう」
- 「ぶんぶんぶん」
- 「カエルの合唱」
- 「ロンドン橋」
- 「チューリップ」
- 「キラキラ星」
- 「むすんでひらいて」
- 「山の音楽家」
ポイント2:バイエルに沿った左手の進み方
第1巻では上に挙げたような曲を右手でメロディを弾き、左手で伴奏をします。
その左手の伴奏が「バイエル教則本」と同じように進んでいきます。
はじめうちは「ソ」のみ。
続いて「ド」と「ソ」の2音による伴奏が続きます。
そして「ドソ」と「シソ」という二つの和音による伴奏になります。
それが「ドミソ」と「シレソ」「シファソ」に展開していきます。
最後にそれぞれの和音をばらした形のアルペジオ伴奏になります。
これが他の調へ応用されていきます。
ポイント3:基本的な和音の進み方
第1、2巻はほとんどの曲がⅠ、Ⅳ、Ⅴの和音による伴奏でできています。
第1巻ではシャープや、他調から借用音はほぼ出てきません。
第2巻では転調やドッペルドミナントは稀にありますが、それでもほとんどが基本の和音の形の伴奏で弾くことができる曲です。
第3巻のバッハ作曲「ト長調のメヌエット」で多声的な曲が登場しますが、全体を通して古典派の雰囲気の曲が多く収録されています。
ポイント4:レッスンの現場で長く親しまれてきた曲が多い
第4、5巻にはピアノの発表会があれば必ずと言っていいほど演奏されるが入っています。
例えば、
- 「すみれ」
- 「人形と夢と目覚め」
- 「花の歌」
- 「トルコ行進曲」
などです。
ピアノを習って数年経った生徒さんが発表会で演奏し、はじめたばかりの生徒さんは「この曲を弾いてみたい」と憧れになるような曲が後半の巻では収録されています。
このテキストに足りないもの
- 左右の手を同じように扱う多声的な曲が少ない
こんな人にオススメ
- シンプルで親しみやすい曲が好きな方
- 古典派の曲が好きな方
- 基本的な和音を覚えたい方
テキスト概要
- 「新訂 ピアノの森」1~5巻
- 著者:田丸信明
- 学研プラス
- 2014年出版
楽しいピアノライフを!